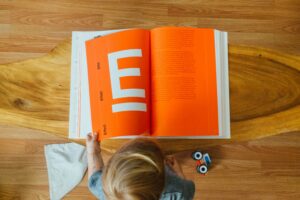絵本の読み聞かせにおける子どもの能力を伸ばす効果、読み聞かせるコツを紹介
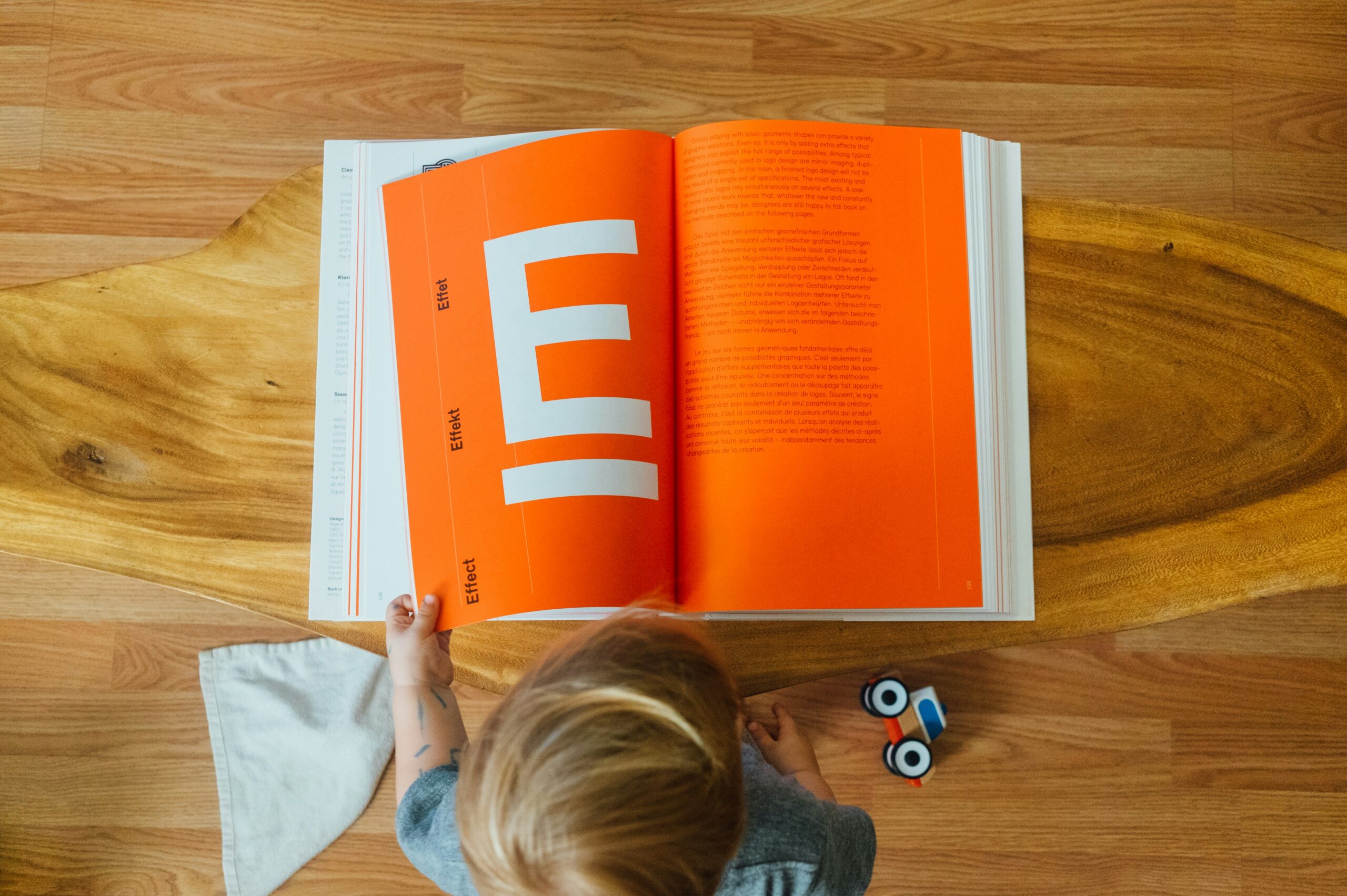
乳幼児は、絵本の読み聞かせが大好きです。言葉を交わして友達になったり、空を飛んだり…。絵本の中の世界は現実の世界では体験できない物事にも出会える空間なので、絵本を読んでいる時間は子ども達にとって“夢の世界を旅できる楽しい時間”といえるでしょう。
また、絵本の読み聞かせは、コミュニケーションを図る手段としてもおすすめです。一緒にワクワクしたり、笑ったり。お子様と素敵な時間が過ごせることでしょう。
今回の記事では、読み聞かせの効果や、効果的な読み聞かせの方法などについてご紹介します。絵本の選び方についても詳しく説明していきますので、ぜひ最後までご覧ください。
絵本の読み聞かせはいつから始めるべき?

絵本の読み聞かせは、いつからはじめても大丈夫です。
子ども達はお母様・お父様の声が大好きなので、絵本の読み聞かせは、大好きな人の声を耳にできる大切な時間になるでしょう。そのため、お子様に“どんな声掛けをしたらいいかわからない”と悩んでいる保護者の方にも絵本の読み聞かせはおすすめといえます。声や言葉に触れる機会になるのはもちろんのこと、話のタネになるので話がはずむようになるからです。
しかし、使用する絵本を月年齢に合わせた絵本にしなければ、お子様にとってたいくつな時間になってしまう可能性があるので注意が必要です。ポイントさえクリアできれば、絵本の読み聞かせはいつからはじめても問題がないので、この機会に絵本選びのポイントも把握するといいでしょう。
【年齢別】読み聞かせの絵本選びとポイント
絵本の読み聞かせを今すぐにはじめていいとわかったところで、絵本選びのポイントについて詳しく説明していきます。より理解しやすいように下記の通り年齢別にわけて記述しますので、ぜひ参考にしてみてください。
- 0歳から1歳までの読み聞かせ
- 1歳から2歳までの読み聞かせ
- 2歳から3歳までの読み聞かせ
ではさっそく、みていきましょう。
0歳から1歳までの読み聞かせ
0歳から1歳の期間は、絵本に親しむ時期です。
赤ちゃんは、生後2〜3ヶ月ごろからものの形や色を認識できるようになりますが、色覚が育つのは4〜5ヶ月前後といわれています。12ヶ月(1歳)になっても、視力はわずか0.1程度なので、しっかりとした色合いの大きなイラストでなければ、把握することは難しいといえるでしょう。
また、文章も単純で短いものがおすすめです。短い文章を“ゆっくり”と“はっきり”と大きな声で読み聞かせるのが0歳から1歳までの読み聞かせのポイントになります。
1歳から2歳までの読み聞かせ
1歳から2歳までの期間は、絵本を好きになる時期です。
この時期は、“絵本は楽しい”や“読み聞かせが好き”など、読み聞かせの時間に興味を持ってもらう大切な時期です。同じ展開が繰り返されるストーリーや、同じリズムの言葉が繰り返される文章など、楽しい気持ちになれる絵本を好む時期なので、リズムよく読み進められる絵本を選ぶようにしましょう。
絵本で何かを学ばせるにはまだ早い時期なので、とにかく楽しむのがおすすめです。リズム感のいい短めの文章を“楽しくハキハキ”読み聞かせるのが、1歳から2歳までの読み聞かせのポイントになります。
2歳から3歳までの読み聞かせ
2歳から3歳までの期間は、絵本を使って学びを深める時期です。
生活習慣や善悪の区別、そして言葉の意味などを絵本を通して学べる時期なので、口頭のみでの指示では理解がしにくい場合などに絵本を活用するのもいいでしょう。絵本を使ってあいさつなどを教えるのも、この時期が最適です。
ただ、この時期は自我が育つ時期でもあるので、好き嫌いがはっきりしている場合があります。もしあまり好きではない絵本がある場合は無理強いをせずに、お子様が喜ぶ絵本を読み聞かせるようにしましょう。
絵本を読み聞かせる効果について

絵本の選び方や読み聞かせのポイントを理解したところで、次は絵本を読み聞かせる効果についてまとめていきます。わかりやすいように8つの項目にわけて説明していきますので、さっそく詳しくみていきましょう。
語彙力の向上
絵本の読み聞かせを通して、お子様はたくさんの言葉や表現に出会うでしょう。いつも耳にする言葉以外の言葉・表現が自然と身につくため、語彙力の向上が期待できます。
語彙力が向上すると自己表現が上手になりますので、人との関わりにも役立てることができるでしょう。
たくさんの言葉を耳にすると、子ども達は意識せずともそれらの言葉を吸収します。そして、耳にした言葉をコミュニケーションを図るための手段として活用するようになるでしょう。何も話せないまま産まれたにもかかわらず、いつの間にか様々な言葉を話せるようになるのは、吸収力の高さがあるからこそ。吸収する能力が高い時期にこそ、絵本の読み聞かせを行うべきといえるでしょう。
感性が育まれる
感性は外の世界の刺激を五感を通して感じ、うまれるものです。絵本の読み聞かせは、視覚にも聴覚にも心地いい刺激を与えるため、感性が育まれていきます。感性が豊かになると物事を様々な角度からとらえられるようになるので、他者の心にも寄り添える優しい子どもに育つでしょう。
想像力・創造力を育む
想像力は、体験・経験したことをもとにイメージをふくらませる力です。そのため、絵本を通して疑似体験することは、想像力を育てる上で役立つでしょう。また、想像力が育つことでアイデアがわきやすくなるので、想像し、造り出す力である“創造力”の成長も期待できるでしょう。
親子のコミュニケーションになる
同じ物事に対して、同じ感情を抱ける“絵本の読み聞かせの時間”は、親子のコミュニケーション時間としてもおすすめです。
例えば、動物園の絵本を読めば動物園に行った気分になれますので、お出かけ気分を味わうための手段としても最適です。お子様とどんな体験・経験をしたいか考えて絵本を選ぶようにすれば、より楽しい読み聞かせ時間になるでしょう。
集中力の向上
絵本を読んでいると「次のストーリーはどうすすむのかな?」と無理なく自然に集中することができます。幼児はまだまだ集中することが難しい時期ですが、集中する時間をくり返し経験することで、集中力が向上していきます。
集中力は今後学習をはじめる際にも必要になる能力です。絵本の読み聞かせを通して、今後の学習につながる力も身につけるといいでしょう。
好奇心を刺激する事ができる
子どもは、心にも身体にも適度な刺激が必要といわれています。絵本の中の世界はドキドキしたり、ワクワクしたり、様々な刺激であふれているので、絵本の読み聞かせによって“好奇心”を刺激することができるでしょう。
好奇心を満たす経験を重ねると、好奇心を満たす喜びを知ります。それによって、物事に興味を抱きやすくなるので知識が豊富な子どもに育つでしょう。
自己肯定感が高まる
読み聞かせを通して得た知識は、お子様の自信につながります。そして、自分のために読み聞かせをしてもらえる時間は、“自分が愛されていることが実感できる幸せな時間”になるでしょう。
そのため、読み聞かせを通して「自信」や「幸せ」を得た子ども達は、自己肯定感も高まると考えられています。
読み手のストレス解消にも
兵庫教育大学大学院連合学校教育学研究科の森慶子氏が発表した 「絵本の読み聞かせ」の効果の脳科学的分析―NIRSによる黙読時、音読時との比較・分析― には、
- 絵本の読み聞かせを行うと聞き手は精神的に落ち着く
- 読み手も朗読に困難を感じない場合はリラックスできる
という検証結果が明記されています。つまり、親子間での絵本の読み聞かせは、お子様だけでなく、お母様・お父様の心を落ち着かせる効果も期待できるのです。
絵本を読み聞かせるコツについて
絵本の読み聞かせについての知識が深まったところで、絵本を読み聞かせるコツについても説明していきます。絵本を読み聞かせるコツは、大きく分けると下記の5つです。
- 表情豊かに、声を変えて、楽しく読む
- 読み聞かせる環境を整える
- 時間を決めて習慣づけする
- 親も一緒に楽しむ
- 途中で「質問」「絵の説明など」をしない
ではさっそく、項目ごとに詳しくみていきましょう。
声を変えて、楽しく読む
子どもの集中力は大人に比べると、とても弱いといわれています。そのため、単調で淡々とした声・スピードで読み聞かせた場合、途中で飽きてしまうことがあるでしょう。
そうならないためにも、抑揚をつけながら読むのがコツです。変化のある楽しい声で読み聞かせるようにしましょう。
読み聞かせる環境を整える
どんなに魅力的な読み方をしても、環境が整っていない場合は子どもの集中が途切れてしまうことがあるでしょう。おもちゃを片づけたり、テレビを消したりして、絵本に集中できる環境に整えてから読み聞かせるのがコツです。布団に入ったときなどに読み聞かせるといいでしょう。
時間を決めて習慣づけする
幼児は“いつもの流れ”や“いつもと同じ”といった、「決まり」「習慣」を好む傾向があります。そのため、絵本の読み聞かせも習慣化するのがおすすめです。
食後や寝る前に読むなど、ぜひご家庭に合った「読み聞かせの時間」をみつけるようにしましょう。

親も一緒に楽しむ
子どもはとてもデリケートなので、お母様・お父様の表情をいつもしっかり観察しています。そのため、お母様・お父様の楽しそうな表情をみるだけで、お子様も幸せな気持ちになるでしょう。
また、顔の表情を確認できない月年齢のお子様にも、声の表情はしっかりと伝わります。不安気に緊張しながら読めば楽しさが半減し、ハキハキと元気に読めば楽しさが増すことでしょう。
絵本の読み聞かせを“知育目的” “教育目的”として子育てに取り入れているご家庭も多いですが、“親子の楽しい時間作り”を目的にすると、笑顔があふれる素敵な親子時間になります。
途中で「質問」「絵の説明など」をしない
絵本に関する内容の質問であっても、読み聞かせの最中は控えさせるのがいいでしょう。途中で質問することにより、子どもの集中力を断ってしまう可能性があるからです。
複数人の聞き手がいる場合などは、読み聞かせの前に「教えて?どうして?は絵本が終わってから」と伝えておけば安心です。ただ稀に、読み聞かせよりも会話が好きなお子様がいらっしゃいます。そのような場合は 絵本を話のタネにして会話を楽しんでいると割り切り、会話を楽しむ時間にするといいでしょう。
絵本の読み聞かせはいつまで行うべき?
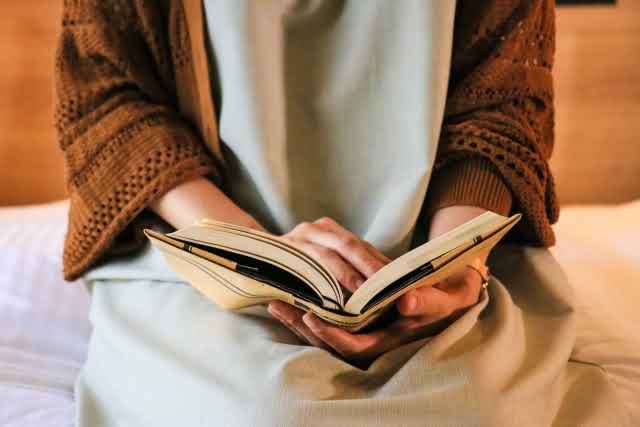
先ほども参考にした 「絵本の読み聞かせ」の効果の脳科学的分析―NIRSによる黙読時、音読時との比較・分析― によれば、聞き手のリフレッシュ効果は成人になっても期待できることが証明されています。実際に老人ホームなどでも読み聞かせが行われていることから、“何歳になったら読み聞かせはしないほうがいい”といった考えは不要でしょう。
お子様が読み聞かせを求めている間はもちろんですが、お子様の情緒が不安定なときなども“絵本の読み聞かせ”をしてあげるのがおすすめです。
読み聞かせに使う絵本は事前に内容を確認すること
読み聞かせに使う絵本は、事前に何度か読んでみるようにしましょう。そうすることで、本当にお子様に読み聞かせたい内容なのか確認することができます。確認を怠ると、意図せずに怖い内容の絵本を読んでしまったり、悲しい内容の絵本を読んでしまったりする場合があるため、はじめて読む絵本の事前確認はとても大切です。
また、くり返し読むことで読み聞かせの際につまずかなくなり、スラスラ読めるようになるでしょう。
読み慣れると、抑揚をつけるのが上手になったり、声の変化が上手になったりします。お子様が喜ぶ読み方で読み聞かせるためにも、初見での読み聞かせは控えるようにしましょう。
同じ絵本を何度も読み聞かせても効果がない?

新しい絵本に触れると「新たな学び」「発見」が多いですが、読み慣れた絵本であっても様々な気づき・学び・効果があると考えられます。
例えば、同じ絵本を使った読み聞かせは、絵本で使用されている言葉・表現をくり返し聞くことで習得がしやすくなるため、語彙力や表現力の向上が期待できるでしょう。また、読み慣れた絵本の読み聞かせは、ストーリーの展開を知っているため安心感を抱きやすくなります。
絵本の読み聞かせにはいくつもの効果があるため、“同じ絵本だと効果がない”ということは決してありません。暗記してしまうほど大好きな読み慣れた絵本であったとしても、笑顔で過ごせる読み聞かせ時間は、親子にとって大切な時間になるといえるでしょう。
まとめ
絵本の読み聞かせは、お子様の能力を伸ばす効果だけでなく、親子の幸せな時間を作るきっかけになります。ぜひ今回の記事を参考にして、絵本の読み聞かせを子育てに取り入れてみてくださいね。
忙しい時でもタブレットで読み聞かせを!見守り知育のススメ
子どもへの読み聞かせを十分に行いたいと思っていても、なかなか時間を割けなかったり、子どもの気分が乗らないこともあると思います。そんな方にぜひ使ってほしいのが天神の幼児タブレットです。
天神の幼児タブレットは読み上げと、文字ハイライト表示が可能です。文字と音をつなげて覚えることで、文字や語彙の獲得につなげられます。タブレットを持たせて、家事をしながら見守り知育が実現します。
読み聞かせ以外の機能も充実の、幼児向け才育型タブレットです。資料をご請求いただくと、パンフレットや価格表などとともに無料体験のご案内をお送りしています。体験では往復送料も無料でタブレットをご自宅までお送りしますので、ご家庭で活用いただけそうかをじっくりご確認いただけます。ぜひ資料をご請求ください。