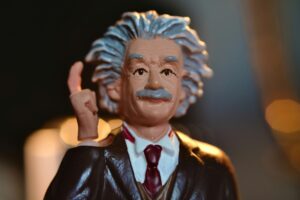【天才かも…】子どもの才能の見極め方と、子どもを天才に育てるために親ができること
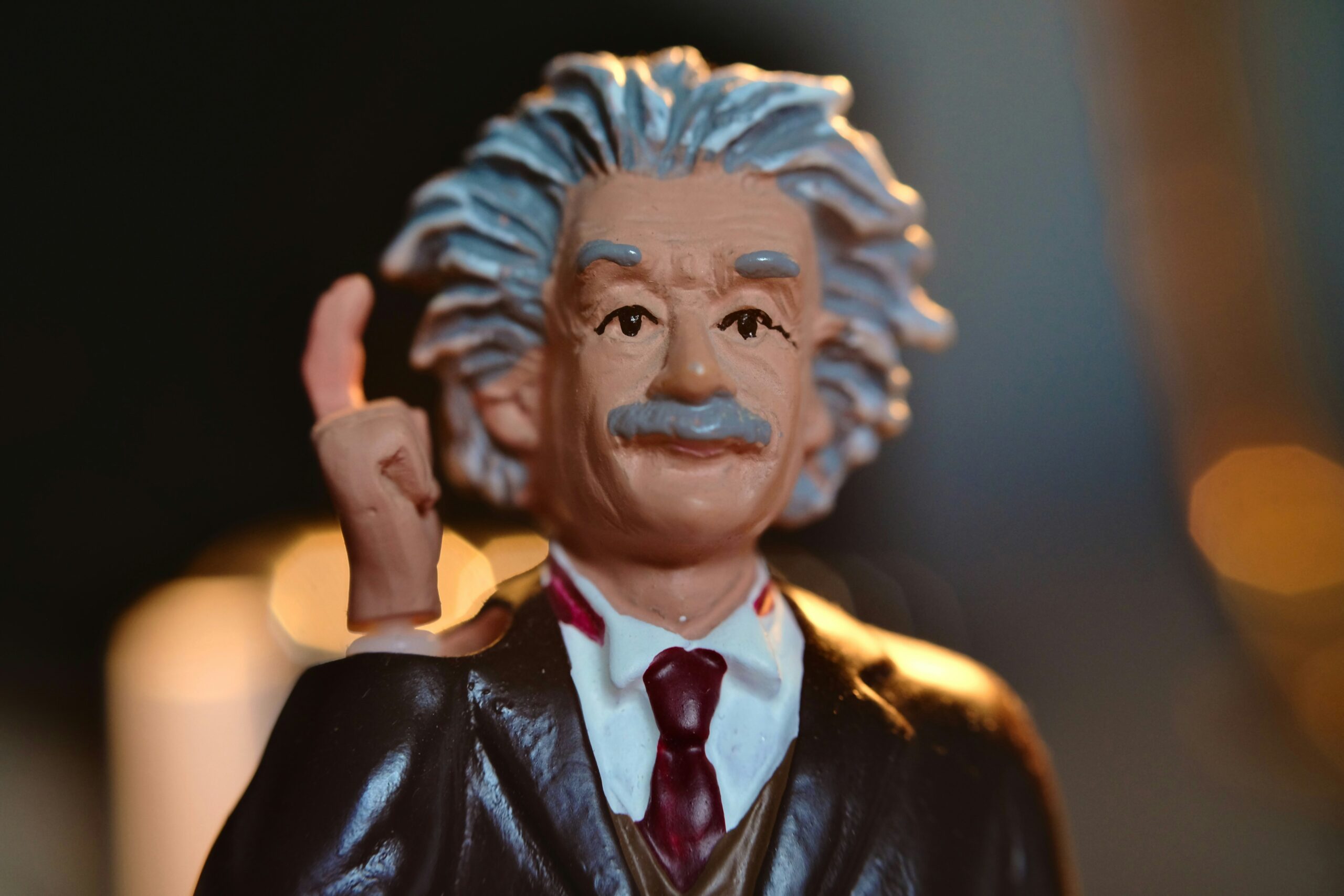
もしもあなたのお子様が、並外れた記憶力を持っていたり、年齢からは想像できないような芸術的な才能があったとしたら…それは「天才」かもしれません。しかし、その秘めた才能が輝き続けるかどうかは、『ご家庭の環境』にかかっているのをご存知でしょうか。
本記事では、天才と呼ばれる子どもの特徴と、子どもの才能を伸ばすために親にできることについてご紹介します。子どもの飛び抜けた才能に気づいたら、ぜひ年齢の垣根を越えてお子様の「能力」に合わせた教育環境を整えましょう。
天才(ギフテッド)とは

天才とは、平均よりもはるかに高い知的能力を持ち、特定分野の技能が人一倍優れていることを指します。日本語では「秀才」「鬼才」などと表現され、外国では「神からの贈り物」という意味でGifted(ギフテッド)と呼ばれます。
日本の文部科学省は、ギフテッドの語を用いず「特定分野に特異な才能のある児童生徒」と表記しています。子どもの才能の発見は、IQ検査で判明するケースが最も多いと言われます。
米国教育省の公表データによると、2018年にギフテッド判定を受けた子どもは、全米の公立学校に通う児童・生徒の「6.6%」、つまり30人学級の1人~2人がギフテッドという結果でした。そのほとんどは「生粋の天才」ではなく、適切な早期教育を受けることで開花する「後天的な天才」と言われます。子どもの特性に合った教育を早く取り入れることが天才を生み出す近道と言えるでしょう。
天才の子どもに見られる能力

天才の子どもには一体どのような能力があるのでしょうか。特に見られる能力として、下記のことが挙げられます。
個人差はありますが、才能のある子どもは、幼児期の頃からある特定のものに長い時間集中して取り遊んだり、一度聞いた音楽や写真を覚えていたり、遊びの中で能力を発揮します。お子様が幼稚園の同級生と同じ遊びで満足しないようであれば、子どもの秘めた才能を試す機会にもなるでしょう。また、小学生になるにつれて、学習の飲み込みが早い、特定分野の興味が強いなど、才能が目に見える形として特徴が表れやすくなります。親としては、このチャンスを逃さずに更なるステップに繋げてあげたいですね。
天才の子どもに見られる性格

天才の子どもに見られる性格としては、主に下記のことが挙げられます。
天才の子どもは、常に多くの知的刺激を満たすために、独自の学習方法で特定の分野を深く掘り下げる傾向にあります。ただこの独創性ゆえに、一般世間では理解されにくく、当たり前の答えも理解できない変わり者という目で評価されることもあるでしょう。結果として、感情のコントロールが難しく周囲と衝突したり、ネガティブな特性と捉えられたりして、日本では特別支援学級に通う例も珍しくありません。
幼少期の天才の特徴

天才の子どもに見られる能力や性格を挙げましたが、「どんな子どもでも当てはまるのでは?」と感じる保護者もいるでしょう。「もしかしたら我が子は天才なのかも…」と見極めるために、ここからは幼少期の天才の特徴について説明します。
群れずに一人で集中していることが多い
天才の子どもは、一人で集中して作業している時間が長い傾向にあります。好きなことや興味のあることへの集中力が非常に高く、関心のあることには徹底的に追い求める特性があるからです。一人で集中する時間が長くても、それを苦と感じない子どもが多いようです。レベルの高い刺激を求めるので、同世代の子どもと遊ぶよりも一人で作業した方が、より楽しさを感じるのでしょう。
疑問が多く、質問数が多い
天才は幼少期から、物事に対して疑問を持ちやすく、質問の数が多いという特徴があります。その理由として、天才の子どもは環境からの刺激に対する感受性が高く、日常にある疑問や矛盾に気づきやすいからです。
世界の発明王であるトーマス・エジソンは、興味がころころ変わり、集中力が長続きしない一方で、驚異的な集中力を持っていたと言われています。小学校の先生が、粘土で「1+1=2」を説明しようとしたところ、「1つの粘土と1つの粘土を合わせると1つの粘土になってしまうのでは?」と質問して、先生を困らせていたようです。
「なぜ」を繰り返して考える癖がある子どもは、探究心が強く、自分の興味のある分野でより活躍しやすいと言えます。
言葉の習得が早い
幼少期の天才は、言葉の習得が早く、年齢に対して並外れた豊富な語彙と複雑な文章構成ができる特徴があります。未就学児のうちに独学で絵本が読めてしまうのもその例です。実際に天才だという当事者は、同級生と話すときにどの言葉なら「通じる」のかを考えるのが日常だったと話しています。それだけ、周囲の友達と語彙(ごい)力が大きく違ったのでしょう。頭の回転も速いのでやや早口で話す傾向もあると言われます。
記憶力が良い
幼少期の天才は、記憶力がずば抜けているという特徴があります。興味のある事柄について好奇心が旺盛で、いつまでも夢中になって課題に取り組む高い集中力があるので、記憶力にも長けているのです。
子どもを天才に育てるために親ができること

天才気質の子どもの発達は、「横並び意識」の強い日本の学校の教育では、能力が伸び止まってしまうケースがあります。そのために、親は子どものレベルを見極め、家庭で下記のような働きかけを実践することが不可欠です。
それぞれ詳しくみていきましょう。
努力できる才能を育ててあげること
子どもの得意分野がある場合は、得意なものに多くの時間をかけて才能を育ててあげる必要があります。天才という領域に達するためには、自分の夢や目標に向かって、全神経を集中して技能の習熟を深める力が求められます。
心理学者のアンダース・エリクソンの研究によると「1万時間の練習(およそ1日3時間を10年間)をせずに名演奏家になった人は皆無」というほど、天才になるためには時間も労力も必要なのです。天才と呼ばれる人たちでさえ、自信を得るには1万時間もかかるということですが、その熟成された時間こそが「プロになりたい」という野心を抱かせるのです。
お子様の得意な能力を突出させて、思いきり能力を発揮する場と没頭できる時間を作ってあげる、「努力できる才能」を磨くことが重要です。
自由に遊ぶ時間を確保する
子どもの才能を伸ばすためには、子どもが自由に遊ぶ時間を確保しましょう。自分で考え行動し、時には失敗も経験してはじめて創造性は培われます。親が先回りして失敗を防いだり、部屋が汚れるのを恐れて遊ぶ範囲を狭くしたりするのは、もったいないことです。
一時汚れることには目をつぶって、子どもの好きを思いっきり体験させてあげる、その時間が子どもの才能をぐんぐん伸ばしてくれます。
様々な経験をさせること
子どもの才能を伸ばすためには、子どもに様々な経験をさせて、選択肢の幅を増やしていく環境作りに努めましょう。特に習い事を通して、「チームプレイが向いているか」「相手との競争が好きか」など子どもの気質が分かります。多くの経験をさせて子どもの反応を確認しながら、お子様の強みを見つけましょう。
自主性、主体性を育ててあげること
子どもの才能を伸ばすためには、子どもが自由に本を読んだり制作に没頭したりできる環境作りが必要です。才能のある子どもは、自分の能力に合わない内容の学習は退屈に感じやすいので、家庭の本棚には子どもの絵本だけでなく、多様な学問分野の本を用意するといいでしょう。
身近に好奇心を刺激する本が揃っていれば、子どもは主体的に知識を吸収し、思考力を伸ばすことができます。

否定せずに褒めてあげること
子どもの才能を伸ばすためには、子どもを否定しないように声かけに注意しましょう。子どもにとって「成功か失敗か」は、親の一言で決まるからです。
例えば、目標とする点数に惜しくも届かなかった場合に、「残念だったね」と声をかければ、それは失敗体験になります。ですが、「今回は1番時間をかけて頑張ったね。次はきっとできるよ」と声をかけると失敗体験にはならないはずです。成果ではなく、具体的な工夫や取り組んだ姿勢を褒める・認めることが大切なのです。
適切な目標設定でモチベーションを保たせること
天才的な子どもの才能を伸ばすには、特定分野において高いレベルの教育を受けられる、そして同じような能力を示す仲間がいる環境に入れてあげることが大切です。「横並び的な学習環境」では、子どもが満足できず退屈する時間を過ごすことになるからです。
子どもが遊んでいる様子をよく観察して、「どの分野に関心があるのか」を見極め、子ども扱いせずにレベルの高い教育環境を与える工夫をしましょう。
才能を伸ばすカギは『家庭教育』

お子様が何に夢中になって遊ぶのか、どのような特性があるのか、しっかり見極めた上で、より高いレベルの環境をたくさん準備する必要があります。子どもを取り巻く今の家庭環境こそが、お子様の思考やアイデアを形にする1番の刺激になります。私たち親は、年齢という垣根にとらわれず、お子様の「才能」を突き抜けさせる、そんなサポーターを目指しましょう。
ここまでご紹介したとおり子どもを天才に育てるために、親ができることとして
等が大事と説明しました。
しかし、家事・育児・仕事などもあるし、それにプラスして色々なことを追加していくのは大変、、、
分かった気がしてもポイントをおさえながら実際にするのは大変そう、、、
などのお悩みをかかえていませんか?
もっと手軽に、負担なく、「子どもの才能」を育ててあげれたらなぁ、、、
と。
自主性や主体性を育てる要素が盛りだくさん。
さらに幼児期に学ぶ内容をまるっと学習できる。
そんな方法があったら試してみたくはありませんか?
などに加え、
さらにママ・パパは幼児教育の知識やスキルも身に付けられる。
そんなツールが「天神」幼児タブレット版です。
今なら自宅にタブレットが届く無料体験も受付していますので、ぜひ試してみてください。
幼児期は脳は6歳までに90%ができあがると言われます。
「幼児教育はまだ早い」と思われている方ほど、早めの取り組みをおすすめ