塾・放デイ・フリースクール・園・学校向け
ICT教材を導入するなら「天神」
放課後等デイサービスに必要なソーシャルスキルトレーニング(SST)とは?
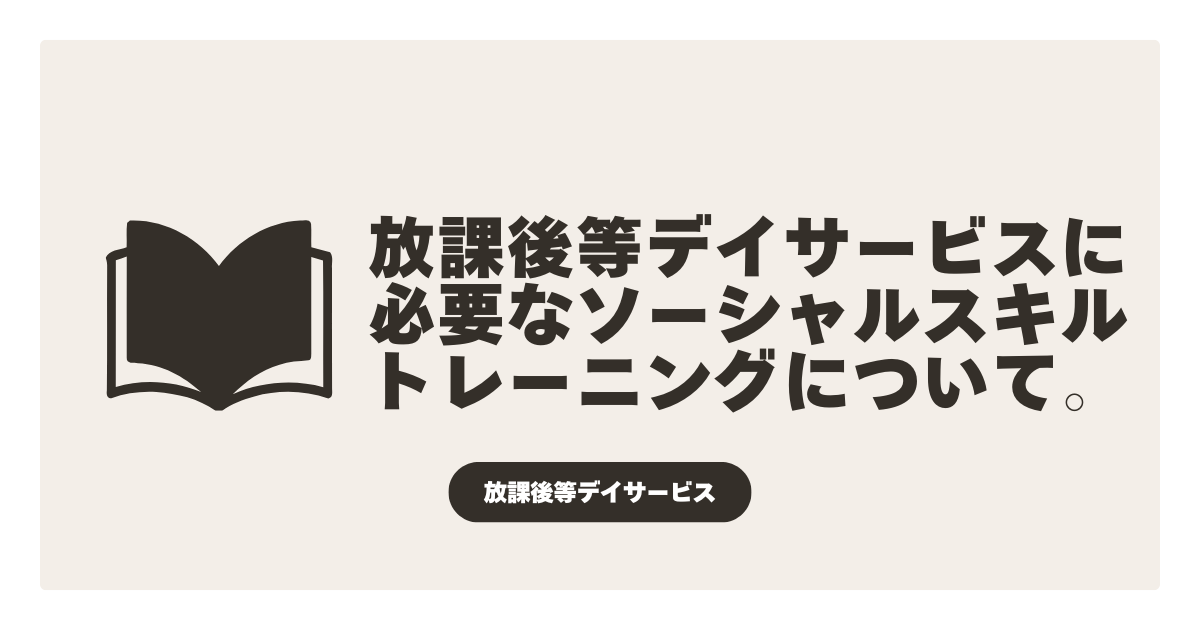
あなたの運営している放課後等デイサービスでは「ソーシャルスキルトレーニング(SST)」(以下:SST)についてどのような取り組みを行っているだろうか?
SSTを実践する上では
「プリントを活用する」「ゲームをする」「ロールプレイをする」など、様々な方法がある。
あなたの放課後等デイサービスでも取り入れているのなら、その取り組みについて、特に問題はないのかもしれない。しかし、そもそもSSTは利用者が社会生活を送る上で必要なスキルを身につけるための重要な療育のひとつであるからこそ、内容は利用者によっても異なるべきであり、それぞれに合ったSSTが必要になってくることが理解できるだろう。
今回は、数々の放課後等デイサービスに導入実績のある天神が「SSTの内容、目的、効果、そして具体的なサービス例」を紹介します。あなたの運営している放課後等デイサービスをのサービスの質をワンランク上げるためにも自社の行っているSSTを見直してみましょう。
放課後等デイサービスは競争の時代に突入し、集客に苦戦されている施設が増えてきています。好調なのは、独自色を打ち出した差別化できている放課後等デイサービスです。その一つが「学習支援」による差別化です。
いくつもの放課後等デイサービスに訪問した営業担当の声をもとに、放課後等デイサービスが学習支援で工夫していることをトップ5にまとめました。
\視覚化?ごほうび?1位は?/
また、現在の集客に関するトレンドについてもウェビナーアーカイブを公開中です。
カギとなるのは「組み合わせ」です。15件の事例を解説中ですので、合わせてご覧ください。
\成功事例15件を大公開中/
放課後等デイサービスにおけるソーシャルスキルトレーニング(SST)の重要性
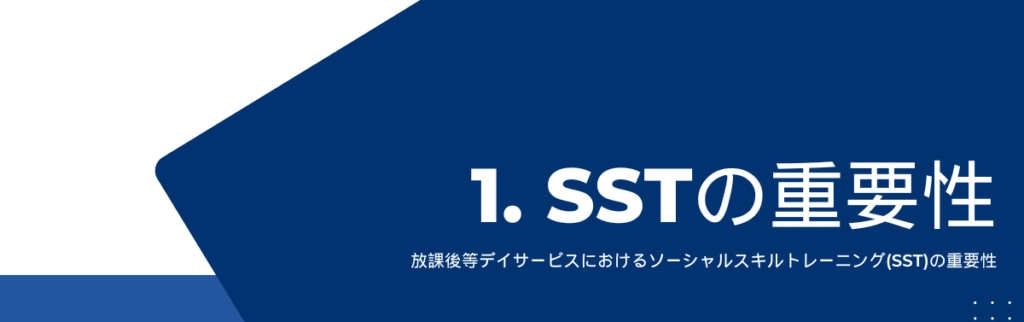
SSTとは?その基本を理解する
SSTは、子どもたちが社会で円滑な人間関係を築き、生活を送る上で必要なスキルを習得するための訓練です。具体的には、コミュニケーション能力、対人関係スキル、問題解決能力などを高めることを目的としています。発達に課題のある子どもたちにとっては、社会生活を送る上で特に重要な支援となります。
SSTは、日常生活における様々な場面での適切な行動を学ぶための実践的なアプローチです。子どもたちは、SSTを通じて、他者との関わり方、感情のコントロール方法、トラブルへの対処法などを身につけることができます。これらのスキルは、学校生活、家庭生活、地域社会での活動において、子どもたちがより快適に過ごすために不可欠です。
また、SSTは、子どもたちが自己肯定感を高め、自信を持って社会生活に参加するための土台を築く役割も果たします。発達に課題のある子どもたちは、社会的な状況を理解したり、適切に対応したりすることに困難を抱えることがありますが、SSTは、そのような困難を克服し、より自立した生活を送るための重要なサポートとなります。
SSTの対象となる利用者
SSTは、発達障害を持つ子どもたちだけでなく、社会生活での困難を抱える様々な子どもたちを対象としています。具体的には、自閉スペクトラム症(ASD)、注意欠如・多動症(ADHD)、学習障害(LD)などの発達障害を持つ子どもたちが対象となることが多いですが、それ以外にも、対人関係が苦手な子ども、コミュニケーションがうまく取れない子ども、感情のコントロールが難しい子どもなど、社会生活を送る上で困難を感じているすべての子どもがSSTの対象となり得ます。
それぞれのニーズに合わせた個別指導が重要となります。子どもたちの発達段階や抱える課題はそれぞれ異なるため、SSTは個々の状況に合わせてカスタマイズされる必要があります。そのため、SSTを行う際には、専門家によるアセスメントに基づいた個別支援計画を作成し、子どもたちの特性やニーズに合わせたプログラムを提供することが求められます。
また、SSTは、子どもたちだけでなく、その家族や関係者に対する支援も含まれることがあります。家庭環境や学校環境を考慮した上で、SSTの効果を最大限に高めるための包括的な支援体制を構築することが重要です。
SSTで得られる具体的な効果
SSTを通じて、コミュニケーション能力の向上、感情のコントロール、問題解決能力の発達など、子どもたちが社会生活を送る上で必要なスキルを総合的に高めることができます。コミュニケーション能力の向上では、相手の話をよく聞き、自分の気持ちを適切に伝えることができるようになります。
また、非言語的なコミュニケーション(表情、ジェスチャーなど)の理解も深まります。感情のコントロールでは、怒りや悲しみなどの感情を適切に認識し、表現することができるようになります。衝動的な行動を抑え、状況に応じた適切な対応ができるようになることも目指します。
問題解決能力の発達では、日常で起こる様々な問題を自分で解決する力が身につきます。状況を分析し、選択肢を考え、適切な解決策を見つけることができるようになります。これらのスキルは、学校生活、家庭生活、地域社会での様々な場面で役立ちます。また、これらのスキルの習得は、子どもたちの自己肯定感や自信を高め、より積極的に社会生活に参加するための土台となります。SSTは、子どもたちがより良い人間関係を築き、社会の中で自立して生きていくための重要なサポートとなるでしょう。
放課後等デイサービスでのSSTの取り組み方

放課後等デイサービスでのSSTの目的
放課後等デイサービスでは、SSTを通じて子どもたちが日常生活で直面する様々な課題に対応できる力を養うことを目的としています。具体的には、友達とのコミュニケーション、学校でのグループ活動、家庭での協力など、子どもたちが日々経験する様々な場面で必要なスキルを習得し、応用できるようになることを目指します。
個別の発達段階やニーズに合わせたプログラムを提供します。子どもたちの発達段階や特性に合わせて、SSTの内容や進め方を柔軟に変更します。例えば、小学校低学年の子どもには、遊びやゲームを取り入れたSSTを行い、高学年の子どもには、より具体的なロールプレイやディスカッションを行うなど、子どもたちが楽しみながら、効果的にスキルを身につけることができるように工夫します。放課後等デイサービスでのSSTは、子どもたちが社会生活を送る上で必要なスキルを総合的に高めることを目的としています。そのため、SSTだけでなく、運動や創作活動、学習支援など、様々なプログラムを組み合わせることで、子どもたちの成長を多角的にサポートします。
また、放課後等デイサービスは、子どもたちが安心して過ごせる居場所としての役割も担っており、子どもたちがリラックスしてSSTに取り組めるような環境を提供します。
具体的なSSTのプログラム内容
プログラムにはさまざまなプログラムがありますが、ここでは大きく分けた4つのプログラムを紹介します。
1.ロールプレイプログラム
ロールプレイを通じて、子どもたちは友達に何かを頼む場面や断る場面、意見が対立した場面など、日常生活で起こりうる社会的な場面を体験します。実際に役割を演じることで、その場面における適切な行動やコミュニケーション方法を学びます。例えば、順番を守る、相手の気持ちを理解する、適切な言葉遣いをするなど、具体的なシナリオを設定し、実践的な練習を行います。このプログラムでは、体験的に学ぶことを通じて、子どもたちが実生活でのスキルを向上させることを目指します。
2.ゲームプログラム
ゲームを活用して、楽しみながら社会的スキルを学ぶプログラムです。このプログラムでは、ルールを守ることの重要性や、相手と協力する姿勢を学びます。例えば、順番待ちやチームでの課題解決を通じて、協調性や自己抑制力を育てます。子どもたちが楽しみながら参加できるため、意欲的に取り組むことができ、学んだスキルを実際の生活で活用できるようになります。
3.ディスカッションプログラム
ディスカッションを通じて、子どもたちは自分の考えを言葉で伝えるスキルや、相手の意見を聞く姿勢を身につけます。このプログラムでは、具体的なテーマを設定し、話し合いを行います。例えば、ある状況でどのように行動すべきかをグループで議論し、意見をまとめる活動を行います。これにより、子どもたちはコミュニケーション能力を高め、他者との関係をより良好に築く力を育てます。
4.成功体験プログラム
このプログラムでは、子どもたちが少しずつスキルを習得し、成功体験を重ねることを重視します。例えば、小さな目標を設定して達成することで、自己肯定感や自信を高めることができます。成功体験を通じて、学んだスキルを実生活で自然に使えるようになることを目指します。どのプログラムにもこの考え方を組み込み、子どもたちが達成感を得られるよう支援します。
これらのプログラムを組み合わせて実施することで、子どもたちが具体的な状況に応じた適切な対応を習得し、社会的スキルを効果的に向上させることができます。
SSTの指導に必要な専門知識
SSTは専門知識がなくても指導は可能ですが、より効果的な指導のためには、発達心理学や特別支援教育に関する知識があると望ましいです。これらの知識を持つことで、子どもたちの発達段階や特性を理解し、一人ひとりに合ったSSTプログラムを計画・実施することができます。
また、SSTに関する専門的な知識やスキルを学ぶことで、子どもたちの行動の背景にある心理的なメカニズムを理解し、より適切な支援を行うことができるようになります。専門的な知識を持つスタッフは、子どもたちの特性を理解した上で、個々のニーズに合わせたSSTプログラムを立案・実施します。
また、SSTの効果を最大限に高めるために、保護者や学校関係者との連携も重視します。専門的な知識と経験を持つスタッフによるSSTは、子どもたちの社会性の発達を大きく促進するでしょう。専門機関では、SSTだけでなく、他の療育プログラムや心理カウンセリングなども提供しており、包括的な支援を受けることができます。
SSTをサポートする教材とツール
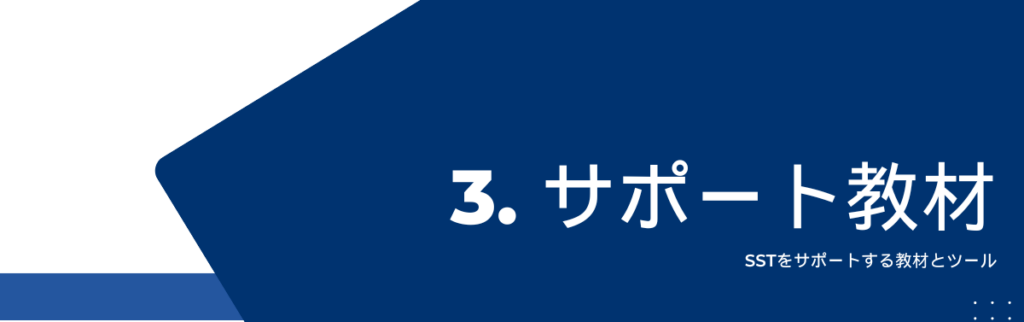
SSTに活用できる教材とツール
SSTの効果を最大限に引き出すためには、教材やツールの活用が効果的です。場面カードや感情チップ、ワークブックなどを活用し、子どもたちの興味を引き出しながら楽しくトレーニングを進めることができます。
場面カードは、様々な社会的な場面をイラストで表現したもので、子どもたちは、その場面でどのような行動をとるのが適切かを考えたり、ロールプレイをしたりする際に活用できます。
感情チップは、様々な感情を表すイラストや言葉が書かれたもので、子どもたちは、自分の感情を認識したり、他者の感情を理解したりする際に活用できます。
ワークブックは、SSTのプログラムに合わせて作成されたもので、子どもたちは、課題に取り組んだり、自分の考えを書き出したりすることで、SSTの内容をより深く理解することができます。
これらの教材やツールは、子どもたちが楽しみながらSSTに取り組むことができるように、視覚的に分かりやすく、魅力的なデザインであることが重要です。また、教材やツールは、子どもたちの発達段階や興味に合わせて選ぶ必要があり、同じ教材でも、使い方を工夫することで、様々な年齢の子どもに対応することができます。SSTの教材やツールは、市販のものだけでなく、手作りのものも活用できます。手作りの教材は、子どもの興味や関心に合わせて、自由に作ることができるため、より効果的なSSTを行うことができます。
教材の選び方と活用方法
子どもの発達段階や課題に合わせて、適切な教材を選ぶことが重要です。教材は、あくまでもトレーニングをサポートする道具として活用し、過度に依存しないように注意しましょう。教材を選ぶ際には、子どもの発達段階や理解度、興味や関心などを考慮し、子どもにとって分かりやすく、使いやすいものを選ぶことが大切です。
また、教材は、SSTのプログラムに合わせて選ぶ必要があり、教材の内容が、SSTの目標と一致しているかを確認する必要があります。教材を活用する際には、子どもが教材の内容を理解しているかを確認しながら、進めることが重要です。また、子どもが教材の使い方を理解していない場合には、丁寧に教える必要があります。教材は、単に提示するだけでなく、子どもが教材を使って、どのように学ぶか、どのようなスキルを身につけるかを意識しながら活用する必要があります。
SSTは、教材を使うことが目的ではなく、教材を活用して、子どもたちが社会生活に必要なスキルを身につけることが目的であることを理解する必要があります。また、教材を使用する際には、子どもの反応を見ながら、必要に応じて教材を変更したり、使い方の工夫をすることも大切です。教材は、SSTを効果的に行うためのツールとして、適切に活用しましょう。
SSTを受けることができる場所
放課後等デイサービス以外にも、SSTは医療機関や療育機関で受けることができます。医療機関では、医師や臨床心理士などの専門家が、SSTを提供しています。医療機関でのSSTは、発達障害の診断を受けている子どもや、精神的な問題を抱えている子どもを対象とすることが多いです。療育機関では、保育士や作業療法士、言語聴覚士などの専門家が、SSTを提供しています。療育機関でのSSTは、発達に遅れが見られる子どもや、障害を持つ子どもを対象とすることが多いです。
専門機関では、発達心理学や特別支援教育の専門家が、SSTの指導を行うだけでなく、SSTに関する研修やコンサルテーションなども提供しています。また、SSTの効果を最大限に高めるために、保護者や学校関係者との連携も重視します。SSTを受ける場所を選ぶ際には、子どもの発達段階や抱える課題、家庭環境などを考慮し、適切な場所を選ぶことが重要です。また、SSTの内容や費用、専門スタッフの有無などを比較検討し、子どもにとって最適な場所を選ぶことが大切です。
ソーシャルスキルトレーニング(SST)の効果をさらに高めるために

家庭との連携の重要性
SSTの効果をさらに高めるためには、家庭との連携が不可欠です。SSTで学んだスキルは、日常生活の中で実践し、定着させていく必要があります。家庭では、SSTで学んだことを振り返ったり、日常生活での具体的な場面を想定して練習したりする機会を設けることが重要です。
家庭での日常生活の中で、SSTで学んだスキルを実践する機会を設け、継続的にサポートすることが重要です。例えば、友達とのトラブルがあった際に、SSTで学んだ問題解決の方法を一緒に考えたり、感情をコントロールする方法を実践したりすることが、SSTの効果を高めることにつながります。
また、SSTの進捗状況や課題について、SSTの指導者と保護者が情報共有し、連携しながら、子どもをサポートすることが重要です。家庭とSSTの指導者が、同じ目標を持って、子どもをサポートすることで、SSTの効果を最大限に引き出すことができます。家庭でのサポートは、SSTの効果を定着させる上で非常に重要であり、SSTを単なる訓練ではなく、生活の一部として取り組むことができるようにすることが理想的です。家庭は、子どもにとって最も安心できる場所であり、SSTで学んだことを安心して実践できる場です。家庭での温かいサポートは、子どもたちの社会性を育む上で、非常に重要な役割を果たします。
継続的なSSTの必要性
SSTは一度受けただけで効果がでるものではありません。継続的にトレーニングを行うことで、徐々にスキルが定着していきます。SSTは、子どもの成長に合わせて、内容を変化させながら、継続的に行うことが重要です。また、SSTの進捗状況を定期的に評価し、子どもの発達段階や課題に合わせて、SSTの内容を調整する必要があります。定期的な振り返りと目標設定が重要です。
SSTの目標は、子どもの発達段階や課題に合わせて、具体的に設定する必要があります。目標を設定する際には、子ども自身も参加させることが、目標達成へのモチベーションを高める上で重要です。目標を達成した際には、子どもを褒めたり、認めたりすることが、自己肯定感や自信を高めることにつながります。また、SSTは、子どもだけでなく、保護者や学校関係者も巻き込んで、チームで取り組むことが重要です。
SSTの効果を高めるためには、継続的なトレーニングと定期的な振り返り、適切な目標設定が不可欠です。SSTは、子どもの成長を長期的にサポートするものであり、焦らず、根気強く取り組むことが大切です。継続的なSSTは、子どもたちが社会生活を円滑に送る上で、欠かせない支援となるでしょう。
まとめ
ソーシャルスキルトレーニングは、子どもたちが社会生活を円滑に送る上で不可欠なスキルを身につけるための重要な療育です。SSTは、コミュニケーション能力、対人関係スキル、問題解決能力など、社会生活を送る上で必要なスキルを総合的に高めることを目的としています。
SSTは、発達障害を持つ子どもたちだけでなく、社会生活を送る上で困難を抱えるすべての子どもたちにとって、非常に有効な支援です。放課後等デイサービスなどの専門機関を活用し、子どもの発達段階や課題に合わせたSSTを受け、社会性を育みましょう。また、SSTだけでなく、運動や創作活動、学習支援など、様々なプログラムを組み合わせることで、子どもたちの成長を多角的にサポートします。SSTは、子どもたちの社会性を育む上で、非常に重要な役割を果たします。SSTを通じて、子どもたちは、自信を持って社会生活に参加できるようになり、より豊かな人生を送ることができるようになるでしょう。
放課後等デイサービスは競争の時代に突入し、集客に苦戦されている施設が増えてきています。好調なのは、独自色を打ち出した差別化できている放課後等デイサービスです。その一つが「学習支援」による差別化です。
いくつもの放課後等デイサービスに訪問した営業担当の声をもとに、放課後等デイサービスが学習支援で工夫していることをトップ5にまとめました。
\視覚化?ごほうび?1位は?/
また、現在の集客に関するトレンドについてもウェビナーアーカイブを公開中です。
カギとなるのは「組み合わせ」です。15件の事例を解説中ですので、合わせてご覧ください。
\成功事例15件を大公開中/
【無料】療育・学習支援を軸とした差別化を、ICT教材「天神」で検討してみませんか?

「天神」は多くの放課後等デイサービスで療育・学習支援のツールとして導入され、差別化に寄与しています。
・社会ルールやマナー、文字の練習など療育的な内容にも対応
・勉強を嫌がる子がスムーズに学習できる
・全国の小中学校の教科書準拠で指導しやすい
・スタッフさんの個人スキルに依存しない指導ができる
・児童ごとの学習カリキュラムを管理しやすい
・音声による読み上げが便利
など様々な評価をいただいています。
詳しくは、資料をご請求ください。
利用者の児童らに使っていただき反応を確認できる無料体験も可能です。
